読者の思い込みをひっくり返すことが、ミステリーの醍醐味。

J-WAVE『Samsung SSD CREATOR'S NOTE』
https://www.j-wave.co.jp/original/creatorsnote/
“いま”を代表するクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないクリエイティブの原点やこれから先のビジョンなど、色々な角度からクリエイティビティに迫る30分。J-WAVE(81.3)毎週土曜日夜21時から放送。
水野:今回のゲストは小説家の辻堂ゆめさんです。

辻堂ゆめ
1992年生まれ。神奈川県藤沢市辻堂出身。東京大学法学部卒業。2015年、『このミステリーがすごい!』大賞優秀賞を受賞し、『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で吉川英治文学新人賞候補。2022年『トリカゴ』で大藪春彦賞受賞。他の著作に『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』『僕と彼女の左手』『二重らせんのスイッチ』『二人目の私が夜歩く』『ダブルマザー』などがある。
湊かなえさんの『告白』がおもしろすぎて…

水野:光栄なことに、辻堂ゆめさんの作品『山ぎは少し明かりて』文庫版に、僕が解説文を書かせていただきました。
『山ぎは少し明かりて』/辻堂ゆめ https://www.shogakukan.co.jp/books/09407525
水野:さらに、辻堂さんはいきものがかりのファンだと。
辻堂:ファンです。大ファンです。
水野:そんなところに甘えつつ、いろんなお話を伺っていきたいと思います。やはり小さい頃から読書はお好きだったのでしょうか。
辻堂:そうですね。小学校に入る前から、絵本をよく読む子どもではありました。母が図書館で、家族全員分のレンタルカードを使って、毎回50冊ぐらい本を借りてきてくれて。私が読み切ると、また借りてきて、ということをしてくれていたんです。だから、毎日何かしらの新しい本を自然と読んでいました。
水野:それがいつ頃から、「自分でも書きたい」となるのですか?
辻堂:いちばん最初というと、絵本を読み始めて間もない4~5歳の頃、2歳の弟が描いた○や△の絵の裏に、ずっと紙芝居を書き続けていたんです。意味不明な絵にストーリーを付与するというか。そういうことを趣味で一生懸命やっていましたね。多分、弟に読み聞かせたりもしていたんですけど、誰かに聞かせたかったというよりは、自分で最初から物語を作るということを楽しんでいたのだと思います。
水野:アメリカに生活拠点を移された時期もあるそうですが、そこでの影響はありますか?

辻堂:中学生になってからアメリカに行ったのですが、小説を本格的に書き始めたのは、アメリカにいた頃なんですよ。それは多分、日本語に飢えていたのだと思います。でも、まわりに借りられる本も買える本もあまりないですし。その閉塞感から、「もう自分で作ろう」と。そして同じ頃、いきものがかりさんの「うるわしきひと」をきっかけにファンになりました。
水野:日本語に飢えるとは、どういう感覚なんでしょう。
辻堂:アメリカは愛国心が強いんですよ。毎日、朝の会で国旗に向かって忠誠を誓うくらい。でもそういうとき内心、「私、本当は日本なんだよな」みたいな感覚になって。それは海外に行ったひとにありがちなことみたいです。すると、どんどん日本が好きになっていくんですよね。それで、日本の音楽を聴いて、日本のドラマをなんとか探して観て、日本の小説に触れたくて自分で書く、という感じになっていったのだと思います。
水野:そこらへんが自然と小説家としてのスタートダッシュにつながっていったんですね。
辻堂:アメリカに行ってなくて、日本で普通に部活などをやっていたら、書き始めてなかったかもしれません。
水野:それを「職業にしよう」と思ったのはどのあたりから?

辻堂:業界によっては、養成所に入らないとプロの道が開かないところも多いじゃないですか。その点、小説の場合は、各出版社が新人賞を主催していて、応募して通ることができたらデビュー。それが中学生にとってもわかりやすかったんです。お金もかからないし、ハードルが低い。だから、職業にすることを目指したというよりは、「せっかく書けたから、新人賞に応募してみよう」みたいな感覚だったんですよね。
水野:最初から書くジャンルの方向性は見えていましたか?
辻堂:見えていませんでした。中学生の頃は、まだミステリーを好んで読んでいたわけでもなくて。思春期の多感なお年頃だったので、純文学のようなよくわからないものを書いて送っていましたね。そして途中から、ミステリーが好きになったんです。
水野:ご自身にミステリーが合うことは、どのように気づかれたのでしょうか。
辻堂:合うというより、おもしろさに気づいた瞬間は明確にあります。高校1年生のとき、湊かなえさんの大ベストセラー小説『告白』がどの書店にも積まれていて。私は一時帰国したとき、成田空港の本屋で買って、帰りの飛行機の13時間を潰そうと思っていたんです。でも、おもしろすぎて2時間で読み終えてしまって。あとの11時間は余韻に浸っていました。そしてアメリカに戻って、「次は絶対にミステリーを書こう」って。
推敲作業がいちばん大変

水野:ミステリーって、どのように書いているんですか?
辻堂:執筆を開始する段階では、もう全体イメージを固めた状態で書くようにしています。伏線を張って、それを回収することが大事になるジャンルなので、まずは綿密なプロットを練るんです。
水野:プロットはどれぐらい細かいものですか?
辻堂:私は小説家のなかでも、かなりプロットを詳しく書くタイプで。長編のプロットだったら、短編小説ぐらいの長さがありますね。忘れたくないことをすべて書いているんです。登場人物の背景や入れたいセリフ、伏線、「この組織は実在する」みたいな情報、雑多なメモなど。執筆のときはもう、プロットに箇条書きになっているものを、どうやっていい文章にしていくかということだけに集中できるようにしています。
水野:それは編集者さんにどれぐらい見せますか?
辻堂:すべてお渡しすると迷惑になってしまうので、ぎゅっとまとめてあらすじぐらいにしたものをお送りしていますね。
水野:プロットの段階で、編集者さんとはどれぐらい会話をされるのでしょう。

辻堂:「ここの流れはおかしいんじゃないか」とか、ミステリーなので、「ここのロジックがちゃんとつながるか」とか、そういう指摘はプロット段階で入れてもらって直しています。物語にしてしまってから直すのは大変なので、なるべく執筆前に解消できるように。
水野:制作のどの段階がいちばん難しいと感じますか?
辻堂:プロットも大変ですけど、私は書き終わったあとの推敲作業ですね。どこまで直すか際限がなくなりそうになったり、妥協しそうになったり、そこの見極めがなかなか難しくて。「自分が満足するまでの時間はどれくらいだろう」というのがブレてしまう。一応、その文章を読んで自分が何も思わなくなったら、直したい欲求が出てこなくなったら、おしまいと決めてはいるのですが。
水野:(推敲が終わる前は)何か違和感を抱く瞬間があるんですね。
辻堂:「この言葉ではないんじゃないか」とか、「もっと100%正しい言葉があるはずだけれど、今は90%くらいしか合ってない気がする」とか。そういう違和感を見つけてしまうと、ずっと考えることになるので、推敲がいちばん大変ですね。
水野:たとえば、それが文庫化されるタイミングでまた作品を読み返してみたときなど、新たに違和感が出てくることもありますか?
辻堂:作家デビューしてから5年目くらいまではありましたね。デビューしたときに書いた作品が、1年から3年ほどかけて文庫化されるんですけど、校正の紙が赤文字だらけになってしまうくらい。恥ずかしさと闘っていました。でも、プロになって5年経ったくらいで、もう読み返しても直したいところがなくなるようになったんです。自分が一度「これでいい」と思ったものがもう変わらない。多分、型ができたのだと思います。
水野:最初の5年で、技術的な成熟などがご自身のなかであって、まとまっていったのでしょうか。
辻堂:おそらくそうですね。文体を模索して徐々に固まっていったり、登場人物の書き方がもう少し精緻なものになっていったり、いろんな変化があって、5年かけてまとまったのだと思います。
読者を驚かせたい

水野:今年8月には作家デビュー10周年を迎えられました。今、ご自身としてはどういうモチベーションで書かれていますか?
辻堂:日々、自分の興味が移り変わっているので、ずっとそれを追いかけたい。そんな心構えですかね。
水野:また、デビュー10周年記念作品として『今日未明』を発表されました。
『今日未明』/辻堂ゆめ https://www.tokuma.jp/book/b666806.html
辻堂:この作品は、最初にニュース速報があって、誰が亡くなったかなどの結果はわかるのですが、「何が真実だったのか」を浮き彫りにする短編5作を入れています。今、たとえばネットのニュースサイトのコメント欄を見ると、情報のない記事に対して、みんながいろんな前提で意見を書き込むじゃないですか。すると、その言葉が既成事実みたいに広まってしまう。そこをミステリー要素も入れつつ、作品にしたかったんです。
水野:それを作品化して伝えることによって、辻堂さんにとっては何が達成されますか?
辻堂:読者の思い込みをひっくり返すことが、ミステリーの醍醐味ですよね。それがこういう社会問題を扱ったテーマでも使えるんじゃないかなと。「こういうひとって、こういう犯罪をするよね」という固定観念や先入観をひっくり返すことによって、「自分には思い込みがあったんだ」と気づいてもらう。少し社会のことを考えるきっかけにもなる。そうやって読者の方をハッとさせることが、私のモチベーションかもしれません。

水野:今後、ミステリー以外のものをどんどん書いていこうという意識はありますか?
辻堂:水野さんに解説を書いていただいた『山ぎは少し明かりて』も、若干ミステリー要素を含む程度で、ミステリー作品ではないんですね。物語のテーマって、ミステリーの枠組みを使ったほうがいいタイプと、それが余計なノイズになってしまうタイプがある気がして。今までも、テーマによってミステリーの濃度を選んできているんです。これからもそういうバランスを探りながら、書いていきたいなとは思っています。
水野:書く動機は変わっていくのでしょうか。
辻堂:私の場合は一貫して、「読者を驚かせたい」という動機があってのミステリーですね。ミステリーの持つ、人間ドラマの要素、感動する部分も好きなんですけど、もうひとつエンターテインメント的な刺激がある。私は、湊かなえさんの『告白』がきっかけでそのおもしろさに気づきました。だから、両方の魅力を詰め込んでいくのが好きなのだと思います。
水野:10周年という区切りを経て、また次の10年も想像されますか?
辻堂:10年後、自分がどんな人間になっているのか、どんな本を書いているのか、想像もつきません。過去10年で、社会の様子や常識も刻々と移り変わっていますし。ただ、そこを切り取ることにおもしろさを感じることが多かったんですね。たとえば、コロナ禍の物語を書いたり。「これはもしかしたら今だけの価値観かもしれない」というものを、次の10年でも切り取っていきたいなとは思っています。
水野:もともとは、「小学校の先生になりたい」という夢があったとも伺っているんですけど、何か下の世代に伝えていきたい気持ちもありますか?
辻堂:伝えていきたいともまた違うのですが、子どもとコミュニケーションを取るのが好きなんですね。たとえば、教育実習に行ったとき、社会人になってからだったので、途中で作家だということがバレまして。校長先生に、「お話を書く授業をやってあげてくれないか」と言われたんです。それで実習生の身で、国語の授業を2時間も担当させていただき、原稿用紙1枚くらいのお話を5年生みんなに書いてもらって。
水野:ものすごく贅沢な授業。
辻堂:そのとき、「先生、僕これがおもしろいのかわからない」って、一段落だけ書いて不満げに持ってきた男子生徒がいたんですよね。でも、その出だしの一文がよかったので、「すごくいいと思う」と褒めたら、急に自信がついて。普段はノートも空白が多かった子なのに、最後まで書いてきたのが私は嬉しくて。伝えることで、子どものクリエイティビティが劇的に膨らんで返ってくることがある。そういうことをやりたいな、みたいな気持ちもありますね。

水野:では最後に、これからクリエイターを目指すひとたちにメッセージをひと言お願いします。
辻堂:クリエイターを目指している方々には、それぞれの心のなかに「これがおもしろい」というものがあると思います。その感性に共感してくれるひとは、きっと世の中にいっぱいいるはず。あとは、表現を磨いて、どういう方向性で形にするのかが、いちばん大変で難しいところで。その挑戦をするにあたり、心折れずに、自分の感性を信じて突き進んでほしいですね。


Samsung SSD CREATOR’S NOTE 公式インスタグラムはこちらから。
文・編集:井出美緒、水野良樹
写真:北川聖人
メイク:内藤歩
番組:J-WAVE『Samsung SSD CREATOR'S NOTE』
毎週土曜夜21時放送
https://www.j-wave.co.jp/

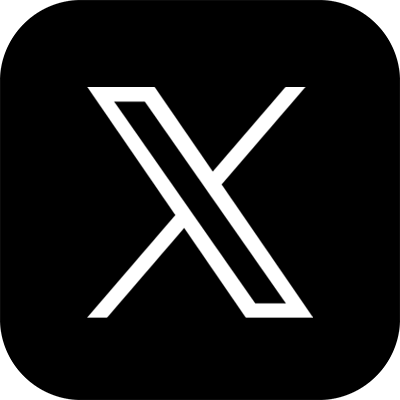



コメント